独立するには?独立・開業に必要な14ステップをご紹介
2024年07月06日
社会人としてキャリアを重ねていく中で、「独立したい」「起業したい」という気持ちを持つ方は少なくありません。
スタートアップ支援なども増え、個人で事業を運営する人も増えていますが、 独立・開業にはいくつかの事務手続きが必要です。
これから独立・起業を考えている方々に向けて、独立・開業前にやっておきたい事前準備をまとめてご紹介します。
目次
①コンセプトを決める

コンセプトとは「お店全体で統一された考え方やデザイン」のことです。
コンセプトをしっかり考えることで、お店の方向性が決まり、開業へのファーストステップとなります。
| What(なにを) | ラーメン |
| Who (だれに) | 小さなお子様連れのファミリー層 |
| Where(どこで) | 国道沿い |
| When(いつ) | ランチタイムから21時まで |
| Why(なぜ) | 自身に小さな子供がいたときに、ラーメンが食べられなかった 近所に新しい住宅地があり、ファミリー層が多いから |
| How(どのように) | キッズルームや駄菓子コーナーを併設して、親も子供も安心してラーメンを食べられるように |
コンセプトに整合性があるか根拠を考えながら精査してみる
整合性がなく、根拠がなければチグハグな経営になってしまい、うまくいきません。
ライバル店舗や参考にしたい店舗と比較してみる
成功している店舗をピックアップして「なぜこの店舗は成功しているのか?」を考えながら、同じく5W1Hに沿って書き出してみましょう。すると、自分のコンセプトの整合性がわかるだけでなく、自社の強みや弱みがわかってきます。
他の人に評価してもらう
自分なりにコンセプトがまとまったら、最後に他の人に評価してもらい、改善しましょう。
②事業計画書を書く

「事業計画書」とは今後どのように事業を運営していくのか、具体的な行動を内外に示す計画書のことです。
日本政策金融公庫や民間の金融機関などに融資を申し込む際にも必要な重要な書類です。
出店エリアや店舗物件にかかる費用、売上予測、自身の給与額予定など、現実的な数字や計画を提示するように心掛けましょう。
思考整理と可視化
事業計画書に改めて書き出すことで、創業者の思考イメージを整理できます。
頭の中で思い描くだけでなく、可視化し、自分の思考を整理するとともに、それを客観的に検討してみましょう。新しい気付きとともにアイデアが生まれるかもしれません。
方向性の共有
起業する際、一人で決める場合もあれば従業員を抱えて法人として始める場合など様々です。
小規模で始める場合、計画はすべて創業者の頭の中にあるため、規模が大きくなった場合に共有するのが難しい…といったことにもなりかねません。
可視化した事業計画書により、「事業が今後どのような方向に進むのか」などを関係者と認識共有すると、迷わず同じ方向を向いて運営できます。社外へアピールする際の材料にもなるでしょう。
資金調達などでのメリット
資金調達の際、資金提供者に対して「どのような事業を何のために進めようとしているのか」「この事業によって何ができるのか」等をアピールしなくてはいけません。その際、口頭での説明は時間がかかり、必要事項がうまく伝わらないことが懸念されます。
もしそこで、相手が知りたい内容をきちんとまとめた事業計画書を提出できれば、口頭での説明よりも短時間で正確に伝えられるため、説得力が増し、審査に合格する可能性が高まります。
③立地を決める

立地条件は業種毎に適したものがあり、利用者の集客ターゲット(商圏)等、様々な要素を吟味して店舗を構える必要があるため、立地選びはとても重要な要素になります。
良い立地のポイント
とある飲食店が「お店をどこで知ったか?」というアンケートを行った結果、約8割のお客様が「お店を見て知った」と回答したそうです。このように、良い立地条件で出店すれば、多くの人に認知してもらえ、チラシや雑誌の掲載を行わなくても、集客が期待できるということです。
良い立地を判断するポイントは以下の3点です。
・想定される営業時間内に見込み客となる人が集まる場所であること
・見込み客の人数に対して、競合がいない、もしくは少ないこと
・分かりやすく、かつ入りやすい物件環境にあること
商圏調査
商圏とは、来店を見込めるお客様が住んでいる範囲のことです。
その商圏内に見込み客がどれだけいるのかを調べ、商売の可能性を事前に把握することがとても大事になります。
商圏調査でやるべきことは以下の2点です。
1.お客様が「10分で来られる範囲か」確認!
お店の規模やコンセプト、販売する商材やサービスによって異なりますが、目安として「10分で来られる範囲」で考えると良いでしょう。
例えば駅前、商店街にあるお店であれば歩いて10分、自転車で10分で来られる範囲で考えます。
2.対象エリアの人口をチェック!
商圏を設定したら、対象エリアの人口を具体的に調べていきます。その際に使用するのが、住民基本台帳です。住民基本台帳は各市区町村のホームページ上で誰でも入手できます。町丁目ごとの居住人数を知ることができるので、商圏内にどれだけの人が住んでいるのか把握しましょう。
競合状況の把握
商圏内に見込み客が大勢いたとしても、競合が多数存在したら商売が難しくなる可能性があります。競合店の規模、距離、提供している商品、サービスのコンセプトによって、どれだけ影響を受ける可能性があるのか、そのリスクを意識しておくことが重要です。
④物件探し

テナント物件を探すにあたって、アパートやマンションなど住宅賃貸物件と同じような探し方の部分も多少はありますが、“店舗” 特有の視点や知識はとても重要です。
希望条件を明確に決めておきましょう
・立地
・坪数(平米数)
・賃料
上記3項目が基本になるので、基準値を明確に決めておくことでスムーズな物件探しが行えます。
物件探しのコツ
未公開物件を見つけましょう
未公開物件とは、不動産業者間で共有していない、ネットにも公開されてない物件情報のことを指します。事業用物件の場合は6ヵ月前に解約予告されることが多く、それが良い物件の場合は募集が公開される前に決まってしまうケースがほとんどです。
想定のエリアが固まったら、実際に現地を歩いて現地広告看板を見つけ、連絡してみましょう。仲介業者に依頼して探してもらうのも手段のひとつですが、仲介業者にお願いしていないオーナーさんもいるので、そういった物件にはこちらから積極的にアプローチすることが大切です。
KINOCOでは、テナントに詳しいスタッフがお客様のご希望に沿ってお部屋探しをお手伝いいたします!
⑤許認可など法律関係の調査

業種によって異なりますが許認可が必要な業種があります。
許認可等(営業許可など)
許認可とは、特定の事業を行うために警察署や保健所、都道府県の行政機関に申請し、取得できる特定の許可のことです。
▶届出:特定の業種を営む場合に行政機関に届出をすることで営業できます。
▶登録:行政機関に申請し、公簿に登録を行うことで営業できます。
▶認可:個人や企業が行う行為に対し、行政庁の合意がないと成立しない場合に申請します。
▶許可(免許):法律で一般的に禁止されている行為に対し、行政機関の審査に合格し適法を行うことで営業が許可されます。
許認可を得ずに無許可で事業を行ってしまうと、営業停止やそれ以上の罰則がある場合があります。事業を行う前に必ず許認可が必要かを確認しましょう。
許認可の申請方法
許認可の申請方法は、事業によって異なるため多岐にわたります。
主に申請窓口の公式HPを訪問し、サイト内にある許認可申請の手順に沿って必要事項を記入していきましょう。
⑥資金調達

開業するにあたり、自身の持っている資金のみでスタートできるのであれば、それがベストです。
自己資金のメリットとし「経営が自由にできる」「返済や利息等の支払いがない」等が挙げられます。
一方で、自己資金として「十分な資金が手元にある」というケースは少なく、その場合、資金を集めなければいけません。
資金調達方法
▶出資:特定の団体や個人から資金の提供を受ける
▶個人借入:銀行の個人ローン等、個人として借りた資金
▶融資:銀行や信用金庫から提供を受ける
▶補助金/助成金:創業補助金や再就職手当等
開業資金の調達先としては、日本政策金融公庫が最も優れています。
全額政府出資の銀行であり、公的役割を経営目標として与えられている機関です。
日本政策金融公庫には、創業者に対して無担保・無保証人で3,000万円までお金を貸してくれる制度があります。新創業融資制度といわれる融資制度で、金利は2%前後です。
その他にも、ビジネスローン、クラウドファンディング等、様々な資金調達の方法がありますが、事業目的やビジネスモデルに合った最適な方法を選択することが重要です。
⑦開業形態を決めて手続きする

開業といっても様々な開業形態があります。事業にあった開業スタイルを選びましょう。
▶個人事業
自営業やフリーランスとも呼ばれ、開業や運営が簡単な開業形態です。
▶株式会社
株式を発行してより多くの人からお金を集めて運営する法人形態です。
▶合同会社
株式会社に近い形態ですが、株式会社に比べて費用が安く、簡単に設立でき、運営の自由度も高い法人形態です。
「個人事業」のメリット &デメリット

・開業手続きが簡単で費用がかからない
・税務申告が簡単
・利益が少ないうちは税負担が少ない
・経理などの事務負担が少ない

・社会的な信用度に劣る
・融資を受けにくい
・人材採用で不利
・利益が多いと税負担が重い
「株式会社」のメリット&デメリット

・多くの人から出資を受けやすい
・社会的信用が高い
・個人事業より節税しやすい

・設立や役員の再任などに費用がかかる
・決算公告の義務
・ 税務や社会保険の手続きが複雑
・利益がなくても法人住民税を払う
⑧税務手続き

個人が新たに事業を開始した場合には、所得税、源泉所得税、消費税に関する各種届出書等の提出が必要となります。
代表的な届出書等は以下の通りです。
個人が新たに事業を始めたときの
所得税、源泉所得税、消費税に関する届出書等とその提出期限の表
| 税目 | 届出書等 | 内容 | 提出期限等 |
|---|---|---|---|
| 所得税 | 個人事業の開廃業等届出書 | ①事業を開始した場合 ②事業所等を開設等した場合 | 事業開始等の日から1ヶ月以内 |
| 所得税の青色申告承認申請書 | 青色申告の承認を受ける場合(青色申告の場合には各種の特典があります。) | 原則、承認を受けようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後に開業した場合には、開業の日から2ヶ月以内) | |
| 青色事業専従者給与に関する届出書 | 青色事業専従者給与額を必要経費に算入する場合 | 青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後開業した場合や新たに事業専従者を有することとなった場合には、その日から2ヶ月以内) | |
| 所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書 | 住所地に代えて事業所等の所在地等を納税地とする場合(変更前の納税地の所轄税務署長に提出します。) | 随時(提出した日後における納税地は事業所等の所在地になります。) | |
| 所得税の棚卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の届出書 | 棚卸資産の評価方法及び減価償却資産の償却方法を選定する場合 | 棚卸資産 ①事業を開始した場合 ②事業を開始した後、新たに他の種類の事業を開始した場合又は事業の種類を変更した場合 減価償却資産 ①事業を開始した場合 ②既に取得している減価償却資産と異なる種類の減価償却資産を取得した場合 ③従来の償却方法と異なる償却方法を選定する事業所を設けた場合 1から5までの事由が生じた日の属する年分の確定申告期限まで | |
| 源泉所得税 | 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書 | 給与等の支払を行う事務所等を開設した場合(「個人事業の開廃業等届出書」を提出する場合を除きます。) | 開設の日から1ヶ月以内 |
| 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 | 給与の支給人員が常時10人未満である給与等の支払者が、給与等から源泉徴収した所得税の納期について年2回にまとめて納付するという特例の適用を受ける場合 | 随時(申請書を提出した月の翌月末までに通知がなければ、申請の翌々月の納付分からこの特例が適用されます。) | |
| 消費税 | 消費税課税事業者選択届出書 | 免税事業者が課税事業者になることを選択する場合 | 選択しようとする課税期間が事業を開始した日の属する課税期間等である場合には、その適用を受けようとする課税期間中 |
| 消費税課税期間特例選択届出書 | 課税期間の短縮を選択する場合 | 選択しようとする課税期間が事業を開始した日の属する課税期間等である場合には、その適用を受けようとする課税期間中 | |
| 消費税簡易課税制度選択届出書 | 簡易課税制度を選択する場合 | 選択しようとする課税期間が事業を開始した日の属する課税期間等である場合には、その適用を受けようとする課税期間中 |
⑨店舗工事

店舗内装にかかる費用は、物件の状態や開業する業種によっても大きく変わってきます。
仮設工事/解体工事/造作工事/設備工事/電気工事/空調工事/塗装工事/排気設備/その他様々な工事の種類があります。
※業種によって工事内容は異なります。
内装工事は予め予算を決めておきましょう。内装工事は様々な理由で追加工事が発生する場合があります。そのような緊急時に備えて、予備のお金を残しておくことも重要です。
⑩仕入れ先や提供商品の決定

顧客ニーズに合った適切な仕入れ・商品決定を行うことが重要です。
取引先業者選定のポイント
1.取引している店舗の評判は良いか
既に取引を行っている店舗の評判を聞くことで、業者のイメージをある程度判断できます。あまり悪い評判が目立つようであれば、良好な関係が築けない場合があるので注意が必要です。
2.信頼できる業者か
取引業者はビジネスパートナーです。信頼関係を築き、良きパートナーとなれるような関係を構築することが重要です。
⑪従業員採用

1.労働条件の通知
従業員を雇用する際は、労働条件を通知必要があります。
2.労働保険・社会保険の手続き
人を雇ったら労働保険、雇用人数によっては社会保険の手続きを進める必要があります。
3.税務署への届出
初めて従業員を雇う際は、税務署に「給与支払事務所等の開設届書」を提出する必要があります。
4.源泉徴収の準備
従業員を雇用したら「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を毎年記入する必要があります。
ハローワークや無料のウェブ媒体等を利用して求人を出しましょう。採用後のミスマッチを防ぐ為にも、求人を募集する際は仕事内容、給与等を明確に記載することが重要です。
⑫集客

顧客ターゲットを設定し、どんなお客さんを呼びたいか明確にしましょう。
自分の会社のコンセプトを明確にすることが大切です。
マーケティングを理解しましょう
お客様に喜んでもらうためにはマーケティングが重要です。マーケティングとは、“どのような価値を提供すればターゲット市場のニーズを満たせるか探り、価値を生み出し顧客に届け、そこから利益を上げること”です。
マーケティングの一環である集客、広告や宣伝にはどのような方法があるか見ていきましょう。
開業時の代表的な集客方法
1.ホームページ
買い物や遊び、外食などの行動を起こす前にインターネット検索する人が多く、集客には欠かせない重要なツールです。
2.Googleビジネスプロフィールへの登録
情報を登録するだけで、Googleマップ上にお店を掲載することができます。
Googleマップを使ってお店を検索する人も多い為、マップ上から直接顧客を呼び込むことができます。
3.SNS
開店後の情報発信としても有効なツールです。開店前から始めてみましょう。
4.ポスティングや新聞折り込み
配布するエリアの選定とチラシの内容が重要になります。
⑬オペレーションを決める
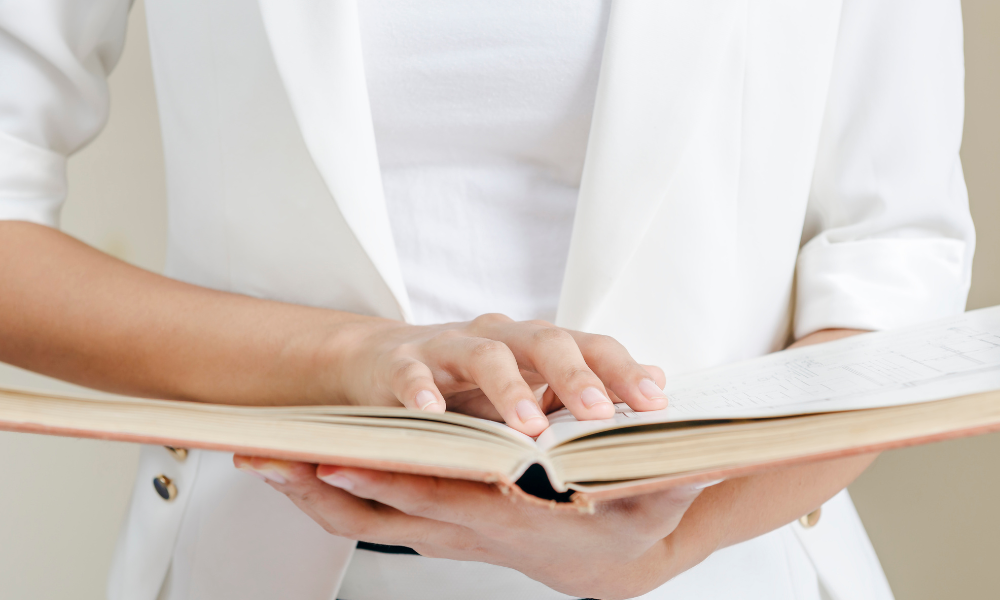
オペレーションとは、店舗運営全般を指し、店舗を運営する上で必要な業務行動のことです。円滑に業務を遂行できるように、オペレーションを単純化し、標準化、均一化させることが重要です。
オペレーションを決めるメリット

・無駄な作業をなくすことで、労力やコストを節約できる
・手の空いた人材を最適な業務に再配置できる
・ルーチンワークをマニュアル化することで、トラブルのリスクを防げる
・ルールに変化を加えることで、従業員のモチベーションや意識を向上させられる
オペレーションの決定・見直しは企業全体の生産性を高めることに繋がるため、重要と言えます。
PDCAサイクルが構築されているか
PDCAを回すことで、オペレーションを改善したり、円滑に進めることができます。
・Plan(計画)
・Do(実行)
・Check(評価)
・Action(改善)
どんなにオペレーションを見直しても、時代や流行の変化により新たな課題や欠陥が見つかることは多々あります。PDCAサイクルを徹底し、オペレーションマネジメントを改善しながら繰り返すことが重要です。
⑭開業届を出す

開業前に行う手続き
お店を開業する際、事業開始から1ヶ月以内に店舗所在地の、所轄税務署長に開業届出書を提出する必要があります。この書類を提出することで、利益が出た場合に税金を納める義務が発生します。
また、従業員を雇用する場合は給与支払い事務所などの開設届も必要です。こちらも事業開始から1ヶ月以内に所轄税務署長まで提出する必要があります。
これらの詳細は国税庁のHPに掲載されているので、不明な点があれば確認しましょう。
※開業届以外にも業種によって提出しなければならない書類が異なるので確認しておきましょう。
開業届とは
正式には「個人事業の開業・廃業等届出書」といい、個人が事業を始めたことを税務署に申告する為の書類です。
開業届を提出するメリット&デメリット

・確定申告で青色申告ができる
・屋号で銀行口座を作れる
・法人用のクレジットカードが持てる
・社会的信用が得られる

・失業手当の対象外になる
・扶養から外される可能性がある
※開業届は法律上の義務はありますが、罰則はありません。
いかがでしたか?事前準備の出来が開業の成否を大きく左右します。しっかりステップに則って準備を進めていきましょう!
KINOCOでは、独立・開業を考えている方の物件探しのサポートを行っております。
お気軽にご相談ください!
\テナント契約までの流れもご紹介/

TEMPORTAL / テンポータル
SNSのフォロワー数3.8万人、Google口コミ評価4.9(747件 / 2025年8月時点)の株式会社KINOCOが運営する福岡市内に特化したテナントサイト。シンプルで分かりやすいデザイン、事業者目線の独自機能で、最適な物件とのマッチングを実現します。







